こんにちは!だんだん寒くなってきましたね。我が家ではホットカーペットを使い始めました、広報の丸山です。2回目の投稿となりますが、まだ緊張しています。
突然ですが、みなさんは東京の寺子屋が何拠点あるかご存知ですか?
秋季プログラムを実施している3拠点のうち、今回は秋季プログラム拠点紹介シリーズの第一弾として足立拠点の紹介をしたいと思います!
【足立拠点の基本情報】
まずは簡単にですが、足立拠点についてご紹介!
対象学年:中学1.2年生
教科:英語・数学
秋季の生徒の人数:13名
秋季の教師の人数:6名
スタッフの人数 :4名
【足立拠点設立の経緯】
足立区寺子屋は前校長のお声掛けによって2012年の夏から始まりました。
そもそも足立区は、経済的要因も影響して、東京23区で最も学力が低い地域と言われています。
「短大・高専・大学・大学院の卒業者比率マップ」
実際に中学校でも経済的に困難な状況にある子どもが多く、学習の遅れも深刻です。しかし集団授業を基本とする学校教育の中だけでは、成績が振るわない子どもの現状に対してサポートすることは難しいというのが現状…。このような状況の中で、学習で躓きを抱える子どもたちが、自信を持って学校生活を送れるようにするために、寺子屋が学校現場に入っていくこととなりました。
【足立拠点の子どもたち】
秋季の足立拠点の子どもは全13名です。寺子屋に通う子どもは低所得世帯に限らず、学校の先生方によって学習支援が必要と判断された学力下位層の子どもたち。また子どもごとに家庭事情や抱える困難は様々です。
英語が中学1年の範囲から、数学であれば小学校の分数の計算から躓いていてしまっている中学2生、一学期の内容ですでに躓き始めてしまった中学1年生。また一度習い、理解したことでも時間が経つと忘れてしまうため、なかなか新しい単元に進むことが出来ない等といった課題も。
そして家庭では保護者の子どもに対する学習意識が低いことが多かったり、兄弟の面倒を見なければいけないことから学習時間を確保出来なかったり…様々な困難を抱える子どもたちがいました。
しかしこのような状況に置かれた子どもたちは、「もっと出来るようになりたい」という気持ちを持っていて、全員が部活に所属しながらも毎週寺子屋に参加したいという意思で寺子屋への参加を決めています。
【これまでの変化】
今回の秋季プログラムで足立区寺子屋は第6期目を迎えています。
2012年度のプログラムでは、子ども一人一人に寄り添った指導等により、子どもが主体に授業に参加したり、苦手な科目にも積極的に取り組むようになったりするなどの成果が見られました。また学習意欲アンケートに大きな向上や、定期テストでの点数の上昇も一部で見られるようになりました。
2013年の春季プログラムでは、1年後に子どもたちが「自立して目標に進んでいける状態」を目標として、子どもが自信や目標を持って楽しく勉強が出来ると共に、子どもの努力が結果に結びつくような指導を行いました。その結果、ほとんどの生徒が成績を上げることが出来ました。
【サマープログラムでの子どもの変化】
第5回目であるサマープログラムに私は教師として参加しました。そこで実際に私が目にした子どもたちの変化についてお話しようと思います。
サマプロ初日の子どもたちは自分に自信がありませんでした。授業中には「私、バカだからさ」「答え合ってないよ」「出来ないかも」などという言葉…。休み時間に「何か夢や将来やりたいことを持っている?」と質問すると、「持っているけど…どうせ叶わないから」という返答…。まだ中学2年生であるのに、夢や希望を持ってワクワクしながら将来を思い描くことが出来ない。
では子どもたちが自分に自信も持てるようになるために、教師が出来ることとは何だろう?
そこで夏の足立拠点が重視したのは勉強への「楽しさ」を感じてもらうこと、そして「圧倒的な結果」を出すことでした。そもそも勉強が楽しくなければ寺子屋は子どもたちにとって苦痛なものになり、続けることは出来ません。逆に勉強の「楽しさ」を知ることが出来れば、一人での学習も継続して行うことが可能。
そして夏に頑張ってきたことやこれまでの努力を結果に結びつけることで、それが子どもたちの自信へと繋がります。そればかりでなく、諦めないで頑張り続ければ出来るようになるということを、学習を通じて実感し、夢に対しても諦めずに頑張ろうと思えるようになるのでは?そのためには「圧倒的な結果」を出すことが何よりも重要な夏となりました。
結果として、この夏に子どもたちは大きく変化をしました。授業中と飛び交う「分かった!」「出来た!」「頑張った!」という言葉、「こんなにたくさん解いたんだ」「こんなに集中したの初めて」という自分自身への気付き。また事後テストから子どもたちが自信を持って書いている様子や基礎が出来るようになっていることも見られました。
そしてサマプロ最終日にはある子どもが私に言ってくれた言葉、「夢に向かって頑張ってみる!そのために今は勉強を頑張らないといけないんだね。」と。たった5日間で子どもたちは、自分の夢について自信を持って語ることが出来るようになり、夢に向かって頑張ろうと思えるようになっていました。
【残っている足立拠点の課題】
第5期目のサマプロでは、今まで以上に飛躍的な学力向上、寺子屋に通うことで寺子屋なしでもやっていけるようになる環境づくりが求められていました。
「寺子屋に通うことで寺子屋なしでもやっていけるように」とは一見矛盾しているように思えますが、これには学校連携拠点だからこそ出てきた課題です。足立拠点は学校との兼ね合いから、寺子屋が生徒を指導することが出来るのは中学2年生まで。つまり寺子屋という場所はいつまでも子どもたちに対して開かれ続ける場所ではない…ということ。
これまで足立区寺子屋は子どもたちに安心感や期待感と学力向上を得ることが出来ましたが、寺子屋なしでもやっていけるような「自立して目標に進んでいける状態」を実現するところまでは完全に出来ていません。
中学2先生が中学3年生になってしまったら寺子屋のように少数クラスで自分に向き合ってくれる学習の場が失われてしまいます。そのため中学2年生の子どもたちが卒業する時、寺子屋なしでもやっていけるように「自立して目標に進んでいける状態」を実現していくことが今後の足立拠点に残された課題と言えるでしょう。
【秋季プログラムでの目標】
このように足立拠点はこれまで努力を重ね、この秋は子どもたちにとって大きな転換点となります。
秋季プログラムで足立拠点のプロジェクトマネージャー(現場責任者)を務める増山珠美に秋季プログラムでの目標を聞いてみました。
秋季寺子屋で一番達成したいこと、それは、『足立拠点で生徒が「学力」と「自律的学習習慣の定着」という結果を出すこと』です。生徒ひとりひとりが、自らの学力の向上を数値で把握し、最終目標である寺子屋がなくとも自立して目標にむかっていける状態に大きく近づいて欲しいと思っています。
この拠点目標の達成のために、私自身が秋の目標として掲げているのは「人を育てられる人を育てる自分になること」です。拠点の他のスタッフが教師と、そして教師が子どもと一緒に変容を遂げていくための環境を全力で整えていきたいと思います。
また、これによって一番達成したい「結果」にコミットすると同時に、スタッフ・教師が人を育てられる人になっていくことで、LFA全体、今後の足立拠点においても、意義深い期にしていきたいと考えています。
そのために、自分自身が常に学習者であり続け、「学びの秋」を誰よりも楽しみたいと思います!
秋季プログラムに参加している足立拠点のスタッフや教師たちは今、結果を出し続けられる秋、子どもが自立する秋にするため、全力で子どもたちと向き合っています。
最後まで読んで下さってありがとうございます。
この記事で寺子屋に興味を持ってくれたそんなあなた! LFAの一番の魅力の一つの研修の記事を是非読んでみて下さい!(→ 事前研修内容のご紹介 )
(文:丸山茜)



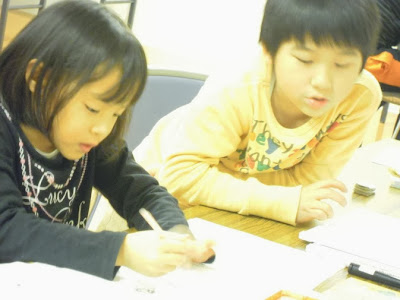










.JPG)

2 コメント:
図もあり全体的に綺麗でよみやすい文章でした。
子供たちの前向きな意見を聞けたことは素晴らしい成果だと思います。
先生のひたむきな努力が子どもの成果を引き出したからこその言葉だということもわかります。
一つ思ったのは、「子どもが最後に前向きな言葉をいった!」ということで満足してるのかないうことです。
子供はいい子ほど、教師の期待が強すぎると最後に何かお礼を言わなきゃ!と先生の期待に応えることをいうものだと思います。
なので、その時は頑張る!といっても次の日からやらなくなるかもしれません。
PMの方の「自立的学習の定着」ということが大切だと思います。子供の言葉もとても大事ですが、それと同じだけ定量的な結果や誰がみても納得する学習習慣の定着を証明するものが求められると思います。
議論をふっかけてすみません汗。でも、きっと皆さんには理解していただけるのではないかと思います。今後の活動に期待しています!!
コメントありがとうございます。
執筆者の丸山です。
ごもっともなご意見だと思います。
「子どもが最後に前向きな言葉をいった!」ということで満足してるのかということですが、嬉しかったことの一つとして皆さんに是非お伝えしたいと思い、紹介させて頂きました。
その時は頑張るといっても次の日からやらなくなることは充分にあり得ると私も認識しています。
そのために寺子屋は子どもたちにとって継続して学習出来る場でなければならないと考えています。
寺子屋がなくなっても子どもたちが自立して学習出来るよう教師やスタッフは現在秋季プログラムを実施しております。
今後もこのようなご意見を頂けると嬉しいです。
コメントを投稿